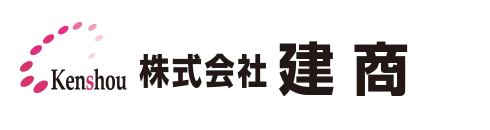BLOGよくわかる解体工事ガイド
![]()
![]()
解体工事で建物にアスベストが使われていたら?除去の流れや費用目安を紹介
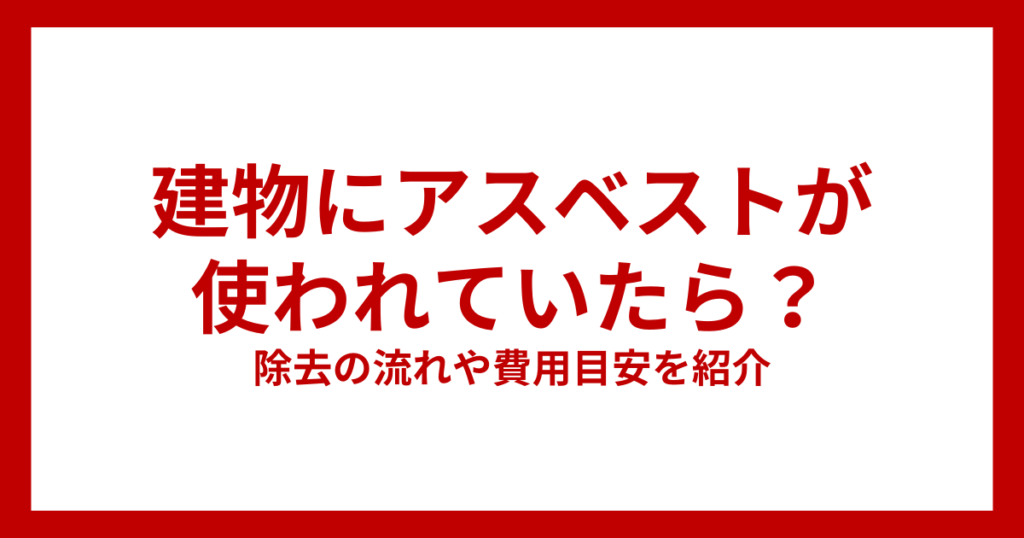
今では有害物質として有名なアスベスト(石綿)ですが、1960年代から2000年代にかけては建材として使用されていました。 深刻な健康被害を引き起こす物資のため、解体工事にあたってはアスベスト含有建材が使われていないかの事前調査が必要です。 さらに、もし解体予定の建物に使われている場合は、法律に則った対応が求められます。 この記事では、アスベストを含んだ建物の解体に関する基礎知識と、アスベスト除去費用の目安、補助金について紹介します。
解体工事の前にはアスベスト使用有無の調査が必要
 石綿障害予防規則等の法令により、解体工事を行う際は、建築物にアスベストが使用されていないか事前調査が必要です。
石綿障害予防規則等の法令により、解体工事を行う際は、建築物にアスベストが使用されていないか事前調査が必要です。
- ・設計図面での調査や目視検査を行う
- ・ケースによっては分析調査も必要
- ・調査結果は3年間保存する
- ・解体工事の作業場所に、調査結果の概要を掲示する
工事現場の規模の大小に関係なく、上記の対応が求められます。 個人宅の解体・改修工事でも「アスベストの調査はしなくてはならない」と覚えておきましょう。 なおアスベストの規制は年々強化されており、2022年以降は以下の対応が追加で必要になります。
- ・2022年4月以降、解体部分の延べ床面積80㎡以上の解体工事の場合、労働基準監督署に電子システムで事前調査結果を報告しなければならない
- ・2023年10月以降、事前調査を行う人は、建築物石綿含有建材調査者などの一定の要件を満たす必要がある
(参考:厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」より) では、建築物のアスベスト使用有無について、解体工事の依頼主があらかじめ把握する方法はあるのでしょうか? 参考になるのが、建築年月と設計図書です。
2006年9月以前に建てられた家は注意
アスベスト含有建材は、2006年9月から全面的に禁止されました。 よって、これ以前に建てられた建築物はアスベストが使用されている可能性があります。 とくに可能性が高いのが、アスベストが使われだした1955年頃から、吹き付けアスベストの規制が始まる1975年までに建てられた建築物です。 吹き付けアスベストとは、セメントとアスベストを混ぜて天井や壁などに付着させる工法。 優れた防火性や断熱性から、ビルや工場といった鉄骨造建築でよく使用されていました。
アスベスト含有建材が使用されていないかも確認しておこう
木造一戸建てのような個人住宅の場合、吹き付けアスベストが使われたケースは多くありません。 しかし、アスベスト含有建材が使われている可能性はあります。 設計図面などから住宅に使用されている建材を調べましょう。 商品名やメーカー、型番のいずれかがわかれば、国土交通省の「石綿(アスベスト)含有建材データベース」でアスベスト含有建材に該当するかがわかります。
解体予定の建物にアスベストを使用されていたら?
 事前調査の結果、アスベストの使用が判明したらどうすればよいのでしょうか? 解体の流れを解説します。
事前調査の結果、アスベストの使用が判明したらどうすればよいのでしょうか? 解体の流れを解説します。
発塵レベルに合わせて対応する
アスベストは、綿のようにふわふわと空気中を漂いやすい物質です。 ただ、その発塵性(飛散のしやすさ)は加工方法によってさまざま。 国土交通省はアスベスト含有建材の発塵性を1〜3のレベルに定めており、解体工事においても発塵レベルに合わせた対応が必要です。
発塵レベル | 建材の種類 | 対応 |
| レベル1 (発塵性が非常に高い) | アスベスト含有吹付け材 |
|
| レベル2 (発塵性が高い) | アスベスト含有耐火被覆材、保温材、断熱材 | |
| レベル3 (発塵性が低い) | その他のアスベスト含有建材(成形板など) |
|
飛散のリスクが高いレベル1、2は大掛かりな飛散防止策が必要です。一方、レベル3では、やや対応の厳しさが緩まります。 前述した通り、木造の戸建て建築でレベル1や2に該当する可能性は高くありません。 多くはレベル3の対応になるでしょう。
アスベストが使われている建物を解体する流れ
アスベストを含んだ建物を解体する流れを簡単に説明します。
1.事前調査
これはすべての建物で必要な部分です。 解体業者は、建築図面や目視確認によりアスベストの使用有無を事前調査し、結果を発注者へ説明します。 ここで「使用されている」と判明した場合は、1〜3のレベルにそった対応が必要になります。
2.届出(レベル1、2のみ)
発塵レベル1、2の場合は、以下の書類を提出します。
- ・レベル1:工事計画届出、特定粉じん排出等作業の実施の届出、建築物解体等作業届
- ・レベル2:特定粉じん排出等作業の実施の届出、建築物解体等作業届
発注者としては、作業開始の14日前までに「特定粉じん排出等作業の実施の届出」を出す義務があります。 解体業者と相談しつつ進めましょう。
3.準備
アスベストの飛散を防ぐため、作業現場の準備を行います。
- ・近隣住民に向けて工事内容を掲示する
- ・足場と養生シートを設置
- ・集じん・排気装置の設置(レベル1、2)
- ・負圧隔離(レベル1、2)
- ・飛散防止剤の散布
レベル3に対して、レベル1、2ではより高いレベルでの暴露防止策が必要です。
4.アスベストの除去作業
作業員は特別教育を受けた上で、保護具や保護衣を身に着けて除去作業を行います。 除去したアスベストは、飛散しないよう密封して保管。 真空圧縮する場合もあります。 保護具や工具に付着したアスベストも除去し、最後に作業場を掃除します。 なおレベル1、2の場合は、現場の隔離を解く前に資格者による現場の目視確認が必要です。
5.処分場へ運搬・廃棄
アスベストの廃棄を廃棄物処理業者に委託する場合、廃棄物処理法により処理委託契約の締結やマニフェスト管理などが必要です。 一般的な解体工事で発生する産業廃棄物と同様に、不法投棄は許されません。 信頼できる業者を選定しましょう。
アスベスト除去費用の目安
 古いデータではありますが、国土交通省がアスベスト除去費用の目安を発表しています。
古いデータではありますが、国土交通省がアスベスト除去費用の目安を発表しています。
除去する面積 | 除去費用の目安 |
| 300㎡以下 | 2.0万円/㎡ ~ 8.5万円/㎡ |
| 300〜1,000㎡ | 1.5万円/㎡ ~ 4.5万円/㎡ |
| 1,000㎡以上 | 1.0万円/㎡ ~ 3.0万円/㎡ |
※上記は吹き付けアスベストの除去費用 ※2007年1月〜12月の施工実績データより算出 ※出典:国土交通省「アスベスト対策Q&A」のQ40より かなり金額に幅があるのがわかりますよね。 実際の見積額も、施工条件や解体業者によって変動します。 築年数や図面から「使われているのでは…」と不安な場合は、あらかじめ除去費用の目安を解体業者に問い合わせておくとよいでしょう。 きちんとした業者なら、誠実に回答してくれるはずです。
吹付けアスベストの調査・除去は補助金制度もある
 民間建築物については、国土交通省が吹付けアスベストの調査費用と除去工事の補助金制度を設定しています。 よって補助金制度のある自治体なら、補助が受けられるかもしれません。 (参考:厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」) 具体的な補助内容や補助金額は地方自治体によって異なります。 例えば、名古屋市では以下のような内容です。
民間建築物については、国土交通省が吹付けアスベストの調査費用と除去工事の補助金制度を設定しています。 よって補助金制度のある自治体なら、補助が受けられるかもしれません。 (参考:厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」) 具体的な補助内容や補助金額は地方自治体によって異なります。 例えば、名古屋市では以下のような内容です。
- ・調査費用の全額、上限15万円
- ・除去費用の2/3、上限120万円
- ・解体工事を予定しているものは対象外
(参考:名古屋市「名古屋市民間既存建築物吹付けアスベスト対策補助事業のご案内」) また岐阜市では以下の内容です。
- ・調査費用の全額、上限9万円
- ・除去費用の2/3、上限200万円
- ・解体工事を予定しているものも対象
(参考:岐阜市「民間建築物吹付けアスベスト対策補助事業について」) まずは解体予定の建物のある自治体の補助金制度を調べてみることをおすすめします。
アスベスト調査への協力や届出は発注者の義務
 大気汚染防止法により、解体工事の発注者は以下の義務を負うとされています。
大気汚染防止法により、解体工事の発注者は以下の義務を負うとされています。
- ・解体業者の行う事前調査に対して、設計図書の提出や費用負担などの協力をしなければならない
- ・届出対象工事の場合は、特定粉じん排出等作業の実施の届出を行う
もし上記に違反して虚偽の届出などを行った場合、3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。 このように発注者側にも義務を負わせる背景には、次のことがあげられます。
- ・事前調査が不十分な事例が相次いだ
- ・除去費用を安くしたい発注者が、業者に圧力をかける恐れがある
業者を選定する立場にある発注者に対して「いい加減な調査で誤魔化したり、適当な飛散防止策でコストを抑えるのはNGですよ」としているわけですね。 アスベストに関しては発注者側にも責任があることを理解し、適切な業者選定を行いましょう。 (参考:環境省「大気汚染防止法及び政省令の改正について」)
アスベストが使用されている建物の解体なら建商へ
アスベストが使用されている建物の解体作業は、使用されている建材の発塵レベルにより3段階に分けられます。 費用面を心配する声も多いのですが、アスベストに関する規制は年々厳しくなっており、罰則規定も設定されています。 補助金の利用も検討しつつ、誠実に対応してくれる解体業者を選びましょう。 建商なら2000件以上の解体工事を手掛けた実績と経験に基づき、アスベストが使用されている建物の解体でもお客様にとってベストなご提案をいたします! 安心できる解体工事のご相談は、ぜひ建商へおまかせください。 お問い合わせはこちらから:株式会社建商 お問い合わせページ
ご相談・お見積り、お気軽に
お問い合わせください!

現地調査から近隣の方へのご挨拶、
産業廃棄物収集運搬処理、
外構工事・駐車場工事まで!