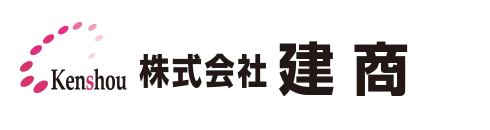BLOGよくわかる解体工事ガイド
![]()
![]()
解体工事の期間はどれくらいかかる?工期が延びる原因と対処法とは
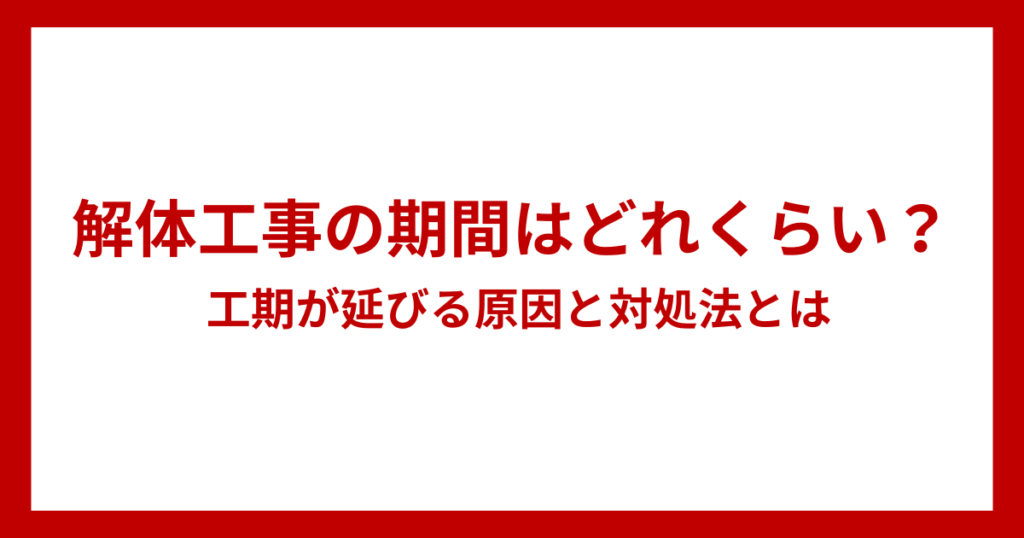
解体工事そのものの期間は、30坪程度の木造家屋であれば約7~10日程度です。 しかし業者選びから引き渡しまでの解体工事全体としてみると1カ月半から2カ月程度は見ておく必要があります。 こちらの記事では、解体工事における期間と工期が延びる原因や対処法について紹介します。 解体工事の途中で工期が延びてその後のスケジュールに困ることのないよう、最後までぜひお読みください。
一軒家の解体期間はどれくらい?大きさ別の工期の目安
 一軒家を解体するのにかかる期間を家の大きさ別に紹介します。 工期の目安として参考にしてください。
一軒家を解体するのにかかる期間を家の大きさ別に紹介します。 工期の目安として参考にしてください。
| 建物の大きさ | かかる工事期間 |
| 10坪程度の小屋や倉庫 | 約2~3日間 |
| 15坪程度平屋木造住宅 | 約4~5日間 |
| 30坪木造住宅(重機使用) | 約7~10日間 |
| 30坪木造住宅(人力) | 約2週間~3週間 |
| 30坪鉄骨造 | 約10日~2週間 |
| 30坪鉄筋コンクリート造 | 2週間以上 |
| 60坪木造住宅 | 約10日~2週間 |
解体工事のスケジュールとそれぞれの工程にかかる日数
ここからはトータルでかかる日数に対して具体的に、それぞれの工程にかかる日数を紹介します。
| スケジュール | かかる期間 |
| トータル | 1カ月半~ |
| 業者選びから契約まで | 約2週間~ |
| 工事着工まで | 約2週間~ |
| 工事期間 | 約7~10日間 |
上の表は一般的な一軒家のサイズ、30坪程度の木造家屋として計算しました。 解体工事は着工まで(業者選びや事前の手続きなど)に意外と時間がかかることがおわかりいただけるでしょうか。 ちなみに工事期間である7~10日間については以下のような内訳です。
- ・足場養生:1日
- ・瓦・内装撤去:1~2日
- ・建物本体の解体:3~5日
- ・足場養生解体:1日
- ・基礎の撤去:1日
- ・整地:半日
なお解体工事全体の流れや業者選びのポイントについては、こちらの記事を参考にしましょう。 関連記事:「解体工事が初めての方へ|全体の流れと業者の選び方、届け出についてなど」
見積もり段階でわかる工期を左右する要素
 あらかじめ見積もり段階でわかる、工期を左右する要素があります。 たとえば解体工事を人力でおこなうのか、それとも重機でおこなうのかによって工期が異なります。 当然、人力でおこなう場合には重機よりも日数がかかるもの。 ならば重機でやってもらいたいと感じるかもしれませんが、現場の周辺環境によってはどうしても重機ではできない場合もあります。 重機ではできないケースが考えられるのは、以下のとおりです。
あらかじめ見積もり段階でわかる、工期を左右する要素があります。 たとえば解体工事を人力でおこなうのか、それとも重機でおこなうのかによって工期が異なります。 当然、人力でおこなう場合には重機よりも日数がかかるもの。 ならば重機でやってもらいたいと感じるかもしれませんが、現場の周辺環境によってはどうしても重機ではできない場合もあります。 重機ではできないケースが考えられるのは、以下のとおりです。
- ・狭小地のため重機が使えない
- ・周辺道路が狭くて重機を搬入できない
- ・周りの環境により騒音を出せないので人力でやる
見積もり段階で現場を業者に見てもらうことで、事前におおよその工期の予想がたてられます。
解体工事がはじまってから工期が遅延する理由
 いざ解体工事がはじまってから工期が延びることも考えられます。 見積もりや契約の段階ではわからなかった、不測の事態によるものです。
いざ解体工事がはじまってから工期が延びることも考えられます。 見積もりや契約の段階ではわからなかった、不測の事態によるものです。
- ・天候が悪い日が続く
- ・近隣からのクレーム
- ・地中埋設物の発見
天候が悪くスケジュール通りに進まない
天候が悪く、工事がスケジュール通りに進まない場合があります。 解体工事に影響を及ぼす悪天候は以下のとおりです。
- ・豪雨
- ・突風
- ・大雪
- ・梅雨時の長雨
通常、重機を使って家屋を解体するときには、粉じんが舞わないように現場に水をかけながら解体していきます。 そのため程よい雨なら好都合にもなりますが、ゲリラ豪雨のような大雨の場合には工事がストップしてしまうのです。 また梅雨時に長雨が続くと、地面がぬかるんでしまいます。 ぬかるんだ地面では、重機が埋まってしまって機能しないため工事を進められません。 さらに突風の中では周辺にホコリや廃材などが飛ばされて非常に危険な場合もあり、風がおさまるまで様子を見ることも。 これらの予想できない悪天候によって、解体工事がスケジュール通りに進まないことは十分考えられるのです。
近隣から工事の音がうるさいとクレームでストップ
 いくら事前に挨拶をしていたとしても、いざ工事が始まると近隣からのクレームによって工事がストップすることもあります。 通常のクレームであれば工事をストップすることはないとしても「やむにやまれない事情」によっては工事を一旦中止することも。 やむにやまれない事情とは、たとえば冠婚葬祭が当てはまります。
いくら事前に挨拶をしていたとしても、いざ工事が始まると近隣からのクレームによって工事がストップすることもあります。 通常のクレームであれば工事をストップすることはないとしても「やむにやまれない事情」によっては工事を一旦中止することも。 やむにやまれない事情とは、たとえば冠婚葬祭が当てはまります。
- ・家人が亡くなり故人を連れ帰ったので葬儀に送り出すまでは静かに過ごしたい
- ・大切な結納をとりおこなう
このような人生で大切な日に「せめてその期間だけは工事を止めてほしい」などと言われれば、対応するしかありません。 とくに不幸な出来事は事前に予想ができないため、その場その場での対応が必要に。 無理に工事を進めると、大きなトラブルに発展してしまう可能性もあるため注意が必要です。
地中埋設物が発見されて工事が中断する
 解体工事を進めていくうちに、地中埋設物が発見されると工事が中断する場合もあります。 簡単に取り除ける場合でしたら工期に影響はありませんが、簡単に取り除けないものが出てきた場合には工事が進められないためです。 他の重機が必要になったり、業者と施主との間で費用の負担についての話し合いが必要になったり、重要な遺跡が発見されれば場合によっては調査が入るケースも。 地中埋設物として考えられるものは、以下のとおりです。
解体工事を進めていくうちに、地中埋設物が発見されると工事が中断する場合もあります。 簡単に取り除ける場合でしたら工期に影響はありませんが、簡単に取り除けないものが出てきた場合には工事が進められないためです。 他の重機が必要になったり、業者と施主との間で費用の負担についての話し合いが必要になったり、重要な遺跡が発見されれば場合によっては調査が入るケースも。 地中埋設物として考えられるものは、以下のとおりです。
- ・コンクリートガラ
- ・建築廃材
- ・古井戸
- ・浄化槽
- ・下水道管
- ・地下室
- ・遺跡
これらのものが発見された場合には、対処法を決めなければなりません。
自然災害で工事ができない
自然災害により、工事が進まないケースもあります。 思わぬ自然災害は、いつ起きても不思議ではありません。 災害にあった場合には工事を進められず工期が延びる場合もあります。
悪質な遅れは損害賠償請求も視野に入れる
 上記のようなやむを得ないケースはしょうがありませんが、悪質な遅れの場合もあります。 誠意のない業者によってあきらかに悪質な遅延であることが判明した場合には、損害賠償請求も視野に入れましょう。 悪質な業者として考えられるのは次のような場合です。
上記のようなやむを得ないケースはしょうがありませんが、悪質な遅れの場合もあります。 誠意のない業者によってあきらかに悪質な遅延であることが判明した場合には、損害賠償請求も視野に入れましょう。 悪質な業者として考えられるのは次のような場合です。
- ・途中で起こる近隣トラブルを放置
- ・許可をもっていないことが判明した(建設業許可もしくは解体工事業登録が必要)
- ・現場にいるのは日本語を話せない外国人スタッフのみで、有事に相談できるスタッフが現場にいない
損害賠償問題に発展しないように、事前の業者選びは大切です。 誠実な対応をしてくれる業者を選びましょう。
解体工事をスムーズに進めるコツ
 解体工事をスムーズに進めるコツは、信頼のおける業者選びです。 次の予定が決まっている場合には、なるべくスムーズに解体工事を進めたいものですよね。 信頼のおける業者に任せれば、それほど大幅な遅れになることはないはず。 関連記事:「解体工事が初めての方へ|全体の流れと業者の選び方、届け出についてなど」 そのうえで、さらに施主としてできることを紹介します。
解体工事をスムーズに進めるコツは、信頼のおける業者選びです。 次の予定が決まっている場合には、なるべくスムーズに解体工事を進めたいものですよね。 信頼のおける業者に任せれば、それほど大幅な遅れになることはないはず。 関連記事:「解体工事が初めての方へ|全体の流れと業者の選び方、届け出についてなど」 そのうえで、さらに施主としてできることを紹介します。
近隣住民との良好な関係と配慮を
近隣の住民との良好な関係を築くように配慮します。 ご近所との良好な関係は、工事をスムーズに進めるために何かと好都合。 工事の前には業者が挨拶に回ってくれる場合も多いのですが、すべてを業者任せではあまり印象がよくありません。 工事前や工事中などもご近所の人と顔が合ったら「今度工事が入りますのでご迷惑をおかけします」と挨拶をしておくとよいでしょう。 解体工事による近隣へかかる迷惑は次のようなものが考えられます。
- ・夜勤が多く昼間寝たいのにうるさくて眠れない
- ・工事の騒音がストレスになる
- ・工事の振動で体調不良になった
- ・工事がうるさくて赤ちゃんが泣き止まない
またご近所と良好な関係が築けていると、たとえば空いている駐車場を快く貸してもらえるなど工事をスムーズに行える利点があります。
余裕をもったスケジュール
季節など鑑みて、あらかじめわかっていることは余裕をもたせたスケジュールをたてましょう。 梅雨時や台風シーズンならば、10日~2週間ほどプラスαで余裕を見る必要があります。 余裕のないスケジュールを組んでしまうと、トラブルがあった時にも強引に工事を進めなくてはなりません。 さらにトラブルが拡大する可能性もあるのです。
事前に不用品はなるべく処分しておく
 解体工事を始める前に、不用品はなるべく自分で処分しておきましょう。 家の中の不用物を片付けるだけでも、手間と時間が案外かかるもの。 家財道具や不用品が残されたままだと、解体工事自体に入る前にまずそれらのものを片付ける必要があります。
解体工事を始める前に、不用品はなるべく自分で処分しておきましょう。 家の中の不用物を片付けるだけでも、手間と時間が案外かかるもの。 家財道具や不用品が残されたままだと、解体工事自体に入る前にまずそれらのものを片付ける必要があります。
工程表をチェックして業者へ進捗確認してみる
解体工事をスムーズに進めるためには、進捗状況を業者へ確認するのも1つの手といえます。 工程表どおりに進んでいれば安心ですし、遅れを早い段階で把握することでスケジュールの調整がしやすくなりますよね。 その際、チェックリストを作っておくことがおすすめ。 チェックリストの各項目が予定どおりに進んでいるのかを、時々チェックしましょう。 関連記事:「解体工事が初めての方へ|全体の流れと業者の選び方、届け出についてなど」
"あなたの家の解体屋さん"建商へぜひご相談を!
 解体工事をスムーズに進めるためには、何か一つが欠けていてもうまく行きません。 一番大切なのは業者選び。 そこで解体工事をご検討の方は、一度建商にご相談ください! 建商なら解体工事をスムーズに進めるポイントがそろっています。
解体工事をスムーズに進めるためには、何か一つが欠けていてもうまく行きません。 一番大切なのは業者選び。 そこで解体工事をご検討の方は、一度建商にご相談ください! 建商なら解体工事をスムーズに進めるポイントがそろっています。
- ・若手からベテランまでの幅広い人力
- ・多彩な重機
- ・どこよりも高い機動力
- ・スタッフの高いモラル
- ・事前の工事スケジュールの明確さ
- ・万が一トラブルの際の対応力
解体工事をお考えなら"あなたの家の解体屋さん"建商へぜひご相談を! お問い合わせはこちらから:株式会社建商 お問い合わせページ
ご相談・お見積り、お気軽に
お問い合わせください!

現地調査から近隣の方へのご挨拶、
産業廃棄物収集運搬処理、
外構工事・駐車場工事まで!